先代から受け継いだ大切な会社を、自分の手でもっと良くしたい。
その一心でDX(デジタルトランスフォーメーション)の旗を振るものの、なぜか現場は冷ややか。「また社長が何か始めたぞ…」という雰囲気を感じ、熱心に説明すればするほど、かつての功労者であるベテラン社員との間に見えない壁が生まれていく…。
そんな孤独なジレンマを抱える、二代目・三代目経営者様は、決して少なくありません。
実はその原因、会社を想うあなたの「熱意」そのものが、意図せず社員の主体性を奪ってしまっていることにあるのかもしれません。この記事では、良かれと思ってやってしまいがちなトップダウンの間違いと、社員が自ら動き出す「共創の文化」の育て方について、私たちの経験から得た具体的なヒントをお伝えします。
社長、その光景に心当たりはありませんか?
あなたは、会社の未来のために、最新のITツールを導入することを決断します。 「これで業務非効率も解消され、生産性も上がるはずだ!」 しかし、数ヶ月後。そのツールはほとんど誰にも使われず、高価な”置物”と化してしまっている…。
あるいは、こうかもしれません。 「来期までに残業時間を30%削減するぞ!」と高い目標を掲げたものの、現場に流れるのは活気ではなく、諦めに似た“しらけムード”。社員のモチベーション低下を感じ、組織の風通しが悪いことに、あなたは一人、頭を抱えている。
これらは、DX推進の現場で驚くほどよく見られる光景です。そして、その失敗の根源には、多くの場合、社長自身がトップダウンで決めてしまった「あること」が共通して存在します。
「自走する組織」への道を阻む、3つの“トップダウンの罠”
会社を前に進めるために、社長のリーダーシップはもちろん不可欠です。しかし、「決めるべきこと」と「現場に委ねるべきこと」を見誤ると、そのリーダーシップは逆効果になってしまいます。
罠1:「使う道具(ITツール)」のトップダウン指定
経営者の目には、最新のツールが組織の課題を解決する「魔法の杖」に見えるものです。しかし、現場の現実から乖離したツール選定は、ほぼ間違いなく失敗します。
なぜなら、現場には経営層からは見えない「かゆいところ」が山ほどあるからです。「この顧客とのやり取りだけは、どうしてもこの形式じゃないとダメなんだ」「あの承認フローには、ベテランの○○さんの長年の勘が欠かせない」といった、数値化できない“現場の常識”。これを無視したツールは、「やらされ感」の塊となり、誰も主体的に使おうとはしません。
私たちの代表、伊藤もかつて、レストランや製造業の現場で壮絶な失敗を経験しました。しかし、その経験から学んだのは、「最高のシステムは、現場の小さな悩みから生まれる」という事実です。ある事務員さんの「この手作業、面倒だな…」という呟きをヒントに、アプリを一緒に作った時、彼女は心から喜んでくれました。その小さな成功が、周りを巻き込む大きな渦の第一歩となったのです。
罠2:「現場無視の目標」のトップダウン設定
「ペーパーレス化率80%達成!」 こうした明確な数値目標は、一見すると効果的に思えます。しかし、その目標が現場の実情を無視した「上からのノルマ」になった瞬間、社員の心は離れていきます。
達成までの道筋が見えない目標は、社員の思考を停止させます。特に、長年の経験で業務の機微を知り尽くしたベテラン社員は、机上の空論の「無理」をすぐに見抜きます。彼らの協力なくして本質的な業務改善はあり得ないのに、トップダウンの目標は、彼らを「変化を嫌う抵抗勢力」というレッテルを貼られかねない状況に追い込んでしまうのです。
大切なのは、「何をすべきか」を細かく指示することではありません。「なぜ、我々は変わる必要があるのか」という目的(WHY)を共有し、「どうすれば達成できるか」を知恵を絞る楽しみを、現場から奪わないことです。
罠3:「完璧なルール」のトップダウン導入
DX推進のために、新しい報告フォーマットや会議体を導入する。これもまた、よくあるアプローチです。しかし、社長や一部の幹部だけで作り上げた“完璧な制度”は、かえって組織を硬直化させる危険性をはらんでいます。
ルールや仕組みが「守るべき絶対のもの」として固定化されると、社員は思考を停止します。「決められたルールなので」「このフォーマットでは報告できません」といった言葉が増え、問題が起きても「ルールが悪い」と、誰もが責任を転嫁し始めるのです。
「自走する組織」とは、いわば“生き物”です。状況の変化に応じて、自らルールを最適化していくしなやかさが必要です。私たちが提供する『共同開発体験セッション』が価値を持つのは、ベテランと若手が一緒になって試行錯誤する、そのプロセス自体にあります。不完全でも、現場の当事者たちの「魂」が宿った仕組みこそが、組織に根付くのです。
では、社長の真の役割とは? — “主役”から“舞台監督”へ
では、社長は何もしなくていいのでしょうか?いいえ、全く逆です。社長にしかできない、最も重要な役割があります。それは、「答え」を与える主役になるのではなく、社員が自ら答えを見つけ、輝くための「舞台」を整えることです。
具体的には、たった3つの行動に集約されます。
- ビジョンを語り、「なぜやるのか」を指し示す ツールや目標ではなく、「この変革を通じて、お客様にどんな価値を提供できる会社になりたいのか」「社員がもっと働きがいのある会社にするために、何を目指すのか」という羅針盤となるビジョンを、あなたの言葉で、情熱を持って語り続けることです。
- 権限を委譲し、「君たちに任せる」と宣言する 「現場のこの課題は、君たちが一番詳しいはずだ。解決策を考え、実行してみてほしい」。そう言って、必要な予算とサポートを約束し、主導権を現場に渡します。そして何より、失敗を恐れずに挑戦できる「心理的安全性」を保証することが、当事者意識を育む上で不可欠です。
- 挑戦を称賛し、「小さな成功」を分かち合う文化を創る どんなに小さな改善でも、うまくいった事例を全社で共有し、挑戦した社員を心から称賛する「場」を意図的に作りましょう。 特に、私たちは**『最初の成功は、ベテランに捧げよ』**という哲学を大切にしています。ベテラン社員の知恵が活かされた改善事例をヒーロー・ヒロインとして称賛することで、彼らは変革の最大の協力者へと変わります。その姿を見た若手社員は、知恵の継承の重要性を学び、世代間の壁は「共創の架け橋」へと変わっていくのです。
学び:DXとは「文化」を創ること
「自走する組織」への道は、一夜にして成るものではありません。 しかし、社長であるあなたが一歩下がり、トップダウンで決めるのをやめ、社員を信じて任せてみる。その小さな変化が、組織全体の大きな変革のスイッチとなります。
DXとは、ITツールを導入することではありません。 それは、社員一人ひとりの知恵と情熱が融合し、会社を未来へと進ませる『共創の文化』そのものを、あなたの会社に納品するプロジェクトなのです。
その第一歩を踏み出すお手伝いができることを、私たちは心から願っています。
「この記事でお話しした内容は私の経験から導き出した『最初の成功は、ベテランに捧げよ』という哲学をベースになっています。私の実体験を交えて、より詳しく解説した動画をご用意しました」 コチラより



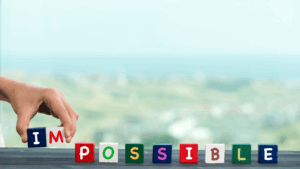

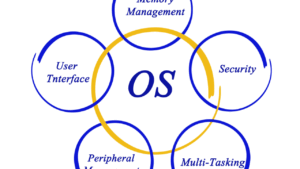

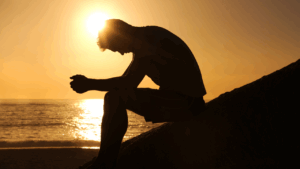


コメント